「自社をさらに発展させ、永続させたい」と考える際、求められる企業努力にはどのようなものがあるでしょうか。数値化しやすく反応が見えやすい例をあげるなら、価格改定、経費削減、従業員満足の向上──国内でも多くの企業がさまざまな取り組みを行なっています。
しかしながら、これらはほんの一例に過ぎません。令和の新時代では他社との差別化や企業価値の向上がこれまで以上に求められており、それらを実現するためには自社が保有する技術や製品の『標準化』が切り札となるのです。
この記事では『標準化』の概要や必要性、実際の活用事例などを解説します。
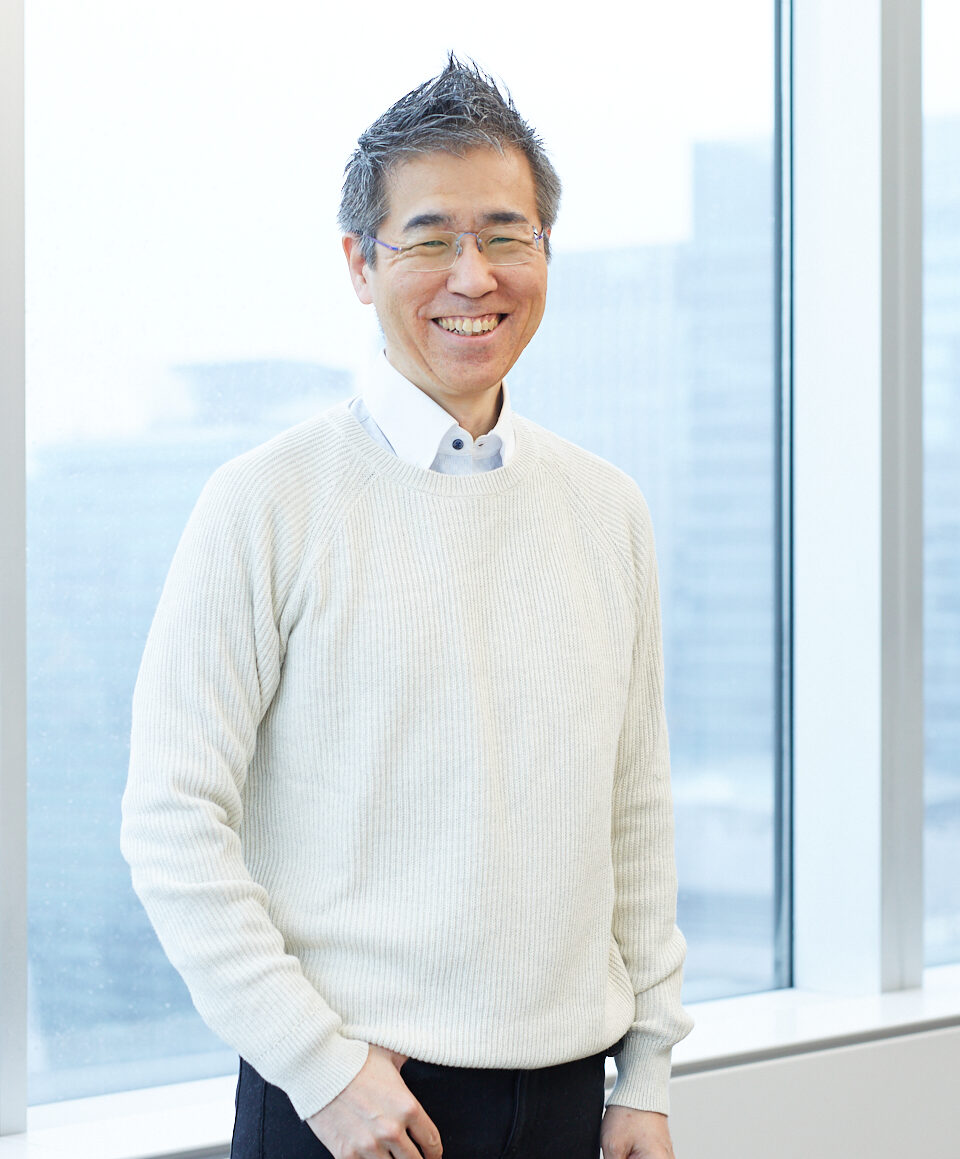 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。私たちの日常に深く根付く『標準化』

『標準化』とは、「標準とされる基準を作ること」および「標準とされる基準に合わせること」を意味します。
たとえばあなたがスマートフォンを新調したとします。購入したのは今まで使用していたものとは異なるメーカーの製品ですが、タッチパネルのキー配列は変わりませんでした。そのため操作方法を一から学び直す必要がなく、仕事やプライベートですぐに活用することができました。
これはスマートフォンのキー配列が『標準化』されているためです。もしもメーカーごとに数字の配列が異なっていたら、緊急連絡時に電話をかけ違ってしまうかもしれません。
また、アルファベットやかなの配列が異なっていたら、メールやチャットのやりとりをスムーズに行なえなくなる可能性もあるでしょう。『標準化』はこのように多様かつ複雑になりやすい製品や工程などに対して、単純かつ秩序だてる役割を持っています。
『標準化』7つのメリット
『標準化』にはさまざまなメリットがあります。
互換性の確保
例にあげたスマートフォンのキー配列のように仕様や形状、寸法などが『標準化』されることで、異なるメーカーの製品に置き換えることができます。
品質の確保
品質マネジメントを『標準化』させることで、定められた基準をクリアした製品が一定の品質を確保していることを意味します。
生産効率の向上
作業工程が『標準化』されることで無駄を省いた簡潔な業務を遂行でき、生産効率の向上へとつながります。
相互理解の促進
『標準化』は共通認識の指標でもあります。たとえば緑色をした非常口の標識などは、大人から子どもまで多くの人々が共通して理解できるマークといえるでしょう。
技術普及
『標準化』されたルールが製造者に広く浸透することで、該当の技術が多くの企業や個人へと普及していきます。
安心、安全の確保
仕様、形状、寸法などが『標準化』されることで、製品を使用する際の安心感や安全性の確保を実現します。たとえば自動車用のシートベルトなどは、事故防止のためにベルトの強度や性能などが定められています。
環境保護
省エネなどの基準も『標準化』が進んでいます。代表的なものでは「統一省エネラベル」。エアコンや冷蔵庫などの製品に付与され、省エネ達成率が数値や色分けでわかりやすく表示されています。
『標準化』の新たな役割
近年、『標準化』において注目されている新たな役割のひとつに「新市場の創造」があります。これまでの解説において、『標準化』に取り組んでいるのは大企業ばかりだというイメージを持たれたかもしれません。
しかしながら、多くの中小企業も優れた製品やオンリーワンの技術を保有しています。これらの知的財産は国内外で新たな市場を創造するための重要な切り札となるのです。
我が国には中小企業における「新市場の創造」を支援する『新市場創造型標準化制度』が存在します。こうした制度を活用することで企業の知的財産に対する信頼性の向上や差別化が後押しされ、競合他社に先んじた「新市場の創造」が現実のものとなるでしょう。
企業の発展を支える知財戦略

ここまで概要や重要性について解説してきましたが、企業が自社の製品や技術を『標準化』させていくにあたって重要となるのが知財戦略です。
ほとんどの大企業では社内に法務部や知財部などの専門部署が設けられています。一方で、多くの中小企業──特にスタートアップ企業においては、知財に対する理解や取り組みが万全であるとはいえません。
充分な専門知識を持つ社員がいなかったり、知財戦略にかける時間や資金などが不足していたりと、多くの企業が最初の第一歩をなかなか踏み出せない状況にあるでしょう。
しかしながら近年ではそうした企業が知財戦略を進めていけるように、政府や大企業があらゆる方法で支援を行なっています。ここでは具体的な事例を踏まえ、戦略の仕組みやメリットについて解説していきます。
事業共創に注力するKDDIの事例
大手通信会社KDDIでは新規事業の積極的な創出を目的に、スタートアップ企業との事業共創を経営方針として打ち出しています。KDDIはスタートアップ企業の成育度に合わせて3段階の事業共創スキームを設定しました。
- 創立から間もない初期段階の企業に対しては「成長支援」
- 中期の段階にある企業には「事業支援」
- 成熟期にある企業には「事業連携」
という区分です。
成長支援
「成長支援」では同社からは出資を伴わず、知財にまつわる考え方や解説、知財啓発などを企業の要望に応じて可能な範囲で行ないます。また、事業共創プラットフォームKDDI∞Labを通じてスタートアップ企業がパートナー企業と実証実験を行ない、ビジネスマッチングの機会を得られます。この実証実験は、KDDIが対象のスタートアップ企業に対して提携や出資を行なうか否かを判断する指標となります。
事業支援
「事業支援」ではコーポレートベンチャーキャピタルである『KDDI Open Innovation Fund』(略称:KOIF)よりスタートアップ企業に対して出資を行なうほか、KDDIグループ傘下のさまざまな事業などとの相乗効果によつ事業創出を推進しています。
事業連携
「事業連携」では対象となるスタートアップ企業が経営において土台が整っている状況であり、KOIFを通さずKDDIから直に出資が行なわれます。
実際に2017年3月期から2019年3月期までの3年間でKDDIが「事業連携」の対象となるスタートアップ企業に対して出資した額は累計5,000億円。両社の信頼関係のもとでKDDIによるM&Aが行なわれることもあり、IoT通信事業の株式会社ソラコムなどが具体例としてあげられます。
『国際標準化』への道のり
『標準化』は大きな括りでは「国家規格」と「国際規格」の2つに分けられます。まず日本国内における『標準化』の代表的な存在がJIS(Japanese Industrial Standard/日本産業規格)、
そして『国際標準化』の代表的な存在がISO規格(International Organization for Standardization/国際標準化機構)です。
JISが認定された製品は海外からの評価や注目度も高く、貿易においてひとつの目安とされています。しかしながら海外で新たな市場を創造していくためには、自社の製品や技術を『国際標準化』させることが望ましいといえるでしょう。ここで着目したいのが「JISのISO規格化」です。
株式会社デンソーウェーブの登録商標である「QRコード」がJISに制定されたのは1999年。

そして翌2000年にはISO規格にも制定されたという事例があります。JISはISO規格をもとに翻案されたものが多く存在しており、「QRコード」は通例とは異なる非常に珍しいケースです。
しかしながら、近年では中小企業における「知的財産のJIS化」を支援する『新市場創造型標準化制度』が経済産業省によって推進されています。こうした制度を活用していくことで中小企業の『標準化』が拡大し、ゆくゆくは『国際標準化』へとさらに躍進していけるのではないでしょうか。
また、『日本知財標準事務所』という知財を標準化することに特化した専門の事務所があります。
この事務所では、新市場創造のためのマーケティングと分析・調査、 施策の実行までトータルサポートを行なっています。標準化について疑問点があればますは問い合わせをしてみてください。
まとめ
いまや企業の永続的な発展と維持に欠かせない取り組みとなった『標準化』。自社の優れた製品や技術を世界中に広めて新市場を創造する切り札──それは革新的な挑戦を続けること、そして政府や大企業の制度をうまく活用していくことではないでしょうか。
参考元:標準化教育プログラム [共通知識編]|吉田 均/「標準化」って なんだろう?|経済産業省

