ー前回は、標準化は身近なところにあるということを具体例を交えて教えていただきました。今回は、実際に標準化していく時のポイントや日本知財標準事務所がどのような役割を担っているかをお聞きしていきます。
▼前編をまだ読んでない方はこちらから
「標準化って聞いたことはあるけどそんな簡単なものじゃないでしょ?」「標準化できること、できる人ってどんな人なの?」という標準化についてのリアルな現状を、今日はインタビューという形で日本知財標準事務所の齋藤さんと藤代さんにお聞きしていきます。[…]
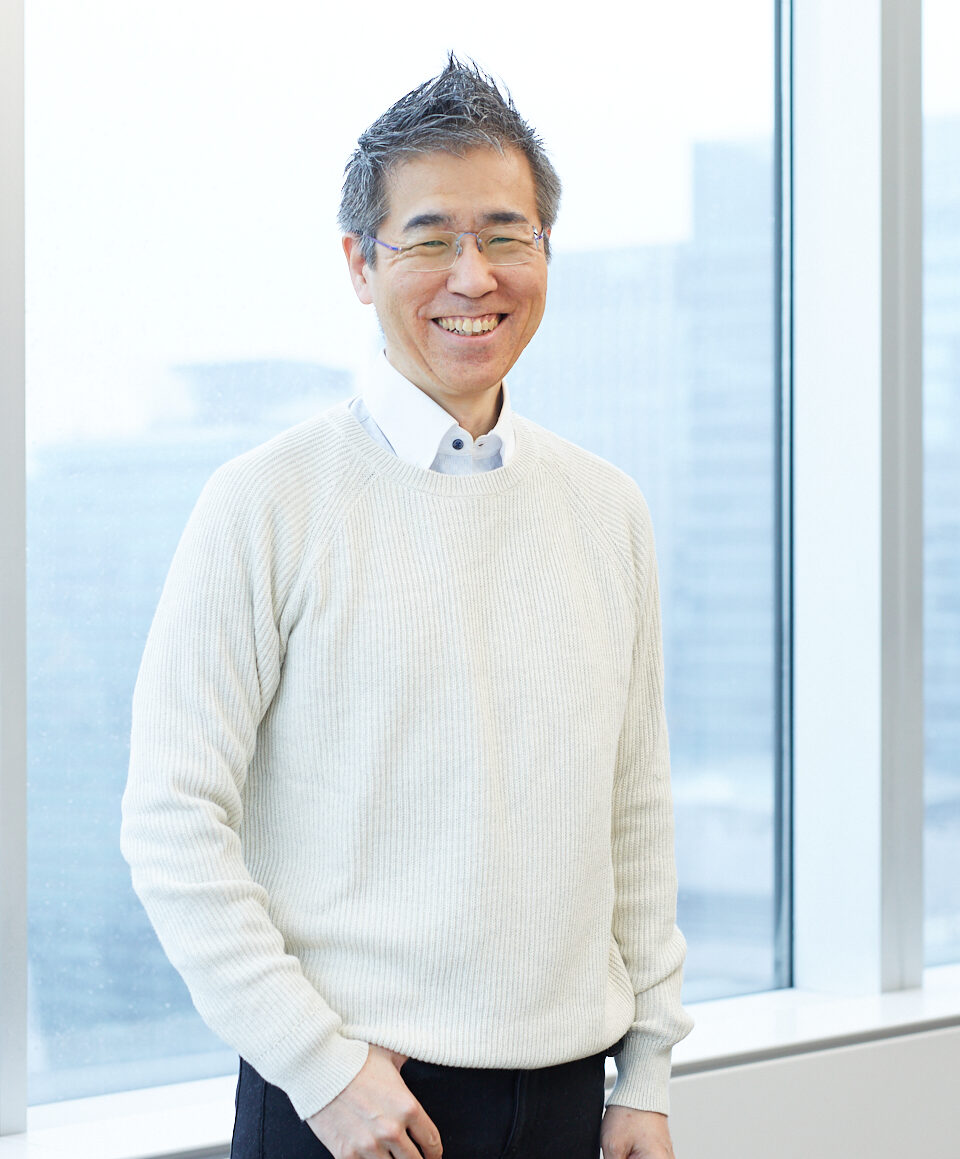 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。標準化の最重要ポイント
ー大成プラスさんのように”モノづくりメーカーからISOの規格を作った”とか、あるいは”仲間づくりをする”、”ユーザーを巻き込む”といった先例を知って「自分たちにも標準化ができるかもしれない」と気付かれた方がいらっしゃるかもしれません。そこで実際に標準化をするにあたって重要なことを教えていただけますか?
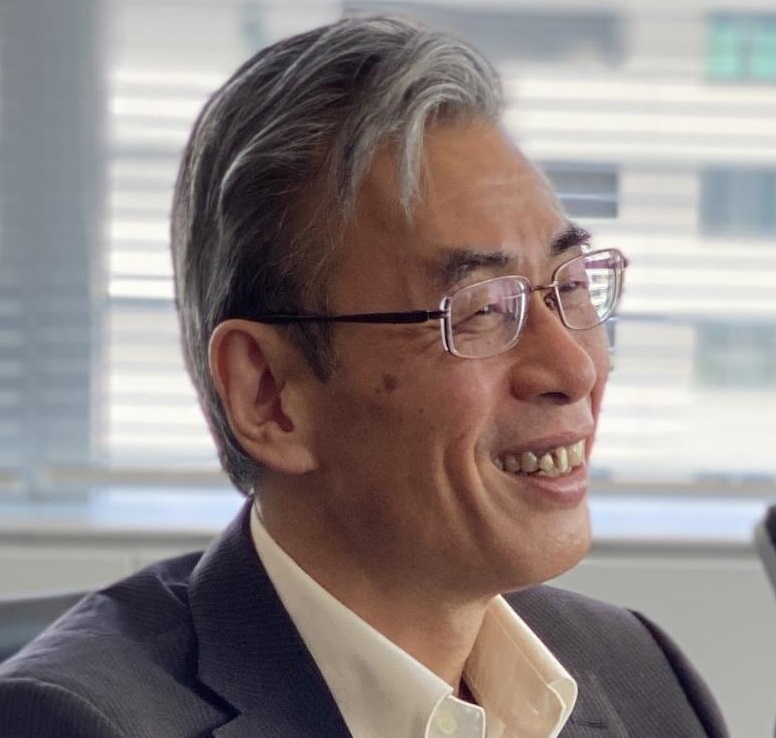
例えば規制だったら国会で国民の代表が集まって議論して決めますよね。じゃあスタンダードはどうやって決めるかというと、これも同じです。
ある製品やサービスに関係する人たちが集まってルールを決めていく。先ほど言った中小企業にしろ大企業にしろ、一社のルールがいずれはJISやISOになるわけなんです。
しかしその企業がライバルメーカーやユーザーさん、関係会社を集めて委員会を作るかというと、それはさすがにルールメイキングに参加する人とその場を提供する人は別のほうがいいですよね。そうでないと金銭問題とか、周りがどうしてもそういう目で見てしまうので。
そういった場合、従来は日本には工業会や学会というものがあって、技術が一つの業界でクロージングしていた。一方で、今はいろんな技術が分野の垣根を越えて絡み合っています。
つまり、昔の技術は工業会・学会がそういった財団法人・社団法人だったので無色透明のお座敷を提供することが出来たけれども、今は技術が輻輳化しているために難しくなっています。もし大企業であってもそんな委員会を立ち上げるのかというと、なかなかそうはいきません。
ー昔とは少し状況が変わってきているということですね。
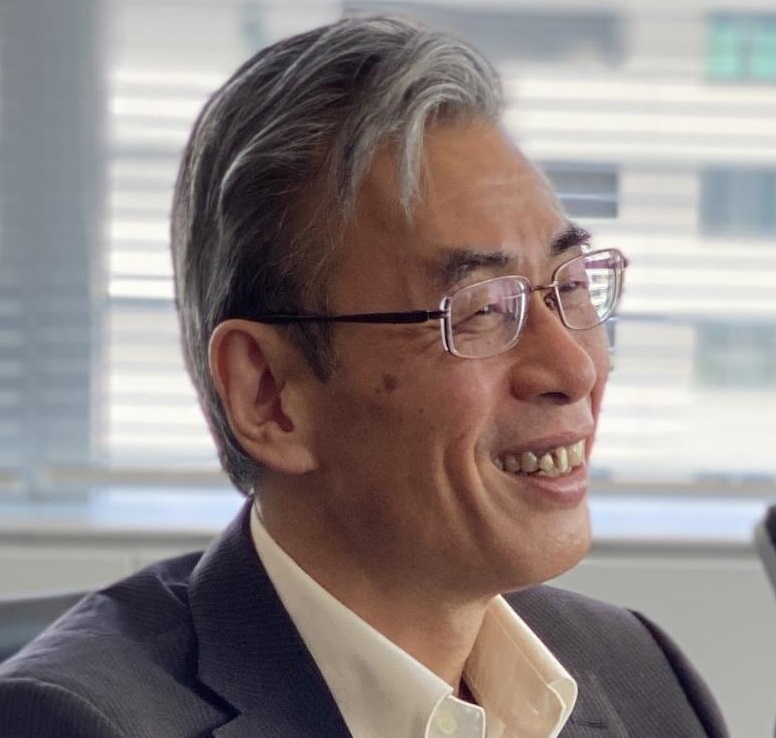
そうなんです。このような状況の中で、我々がそういったお座敷を提供してそこでルールを作るか作らないかを議論して、じゃあ「ルールを作ろう」となってきた時、その中で「自分も積極的に参加します」という人たちをまとめて、要はルール作りを先導する。
ただ、ルールそのものは技術を持っている人が全てなので、そういった方たちの役割分担をはじめ、その『ルール形成の場を提供する』といったお手伝いを私たちができればと考えています。
一企業や一人じゃ絶対ルールというものは作れない一方で、かといってじゃあその人が「このゆびとまれ」という風に関係者を集められるかというとなかなかうまくいかないんです。
であれば「私たちがそういったお手伝いをしましょう」といったことをスタンダード・ゼロのレポートで提供しようかなと思っています。
日本知財標準事務所の存在意義


例えば具体的な例でいくと、素材とかパーツですね。日本企業で強いって言われている分野なんです。完成品やサービスに関しては、だいたいアメリカとかヨーロッパの企業が強いんです。
スマホをはじめとして、なんとなくイメージできると思います。村田製作所さんのセンサーとかシャープさんの液晶とか、主要パーツは全部日本製なんですよ。でも見事に iPhone はアメリカ製ですよね。どうしたら自分達の素材やパーツが組み込ませるか。
完成品・サービスが自分の色に少しでも染められるか、と考えると、やっぱりお客さんが大事ですよね。お客さんをいかに巻き込むかっていう話で、さっき藤代さんの話にも出ましたけど、自分たちの業界だけで集まってもそれは皆敵ですからそこはまとまりはないわけです。
でもお客さんを入れる、少なくとも一団体入れることによって場ができますよね。それで、一緒にWin-Winでこういうプロダクト・市場を作っていきませんかっていう声がけができるわけですが、それをメーカー自身がやっちゃうと変ですよね。要するに売りたいんですよね、みたいになってしまうので(笑)。
そうではなくて、我々のようなコンサルをやっている第三者が声がけをして、同業者だけではなくて、お客さんや一般消費者も含めて「どういったプロダクトだったら嬉しいですか」といった話をしてもらう。要するにバリューチェーンを築き上げるんです。
この高い層を巻き込んで場を作るっていうのは、逆に言うと我々みたいな第三者にしかできないことなので。欧米では普通に民間企業がやっていることなんですけど、日本ではさっきの話があるので珍しいと思われるかもしれませんね。ですが普通にやればいいことなので、それをまず日本で場づくりを提供しようというのがこの事務所の原点です。
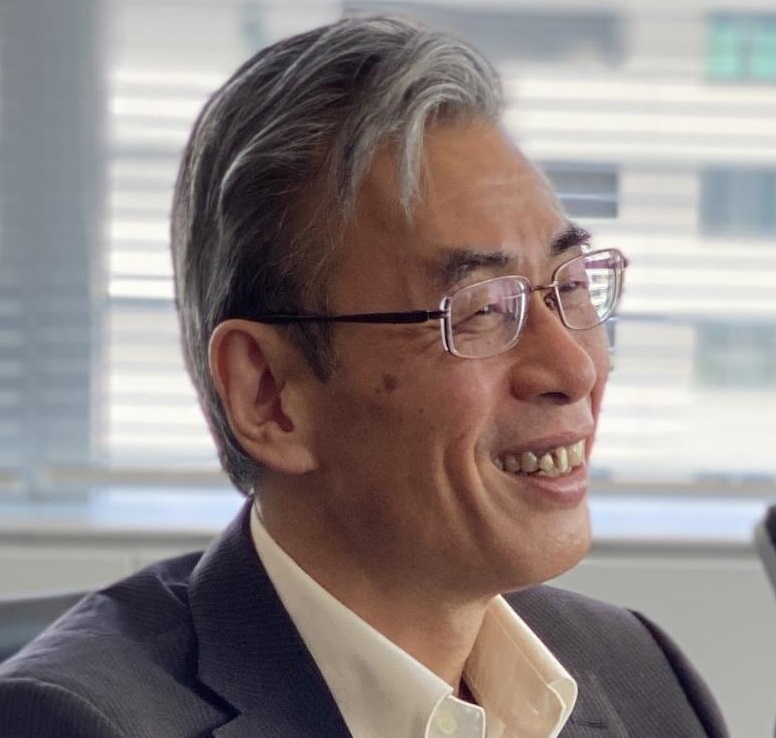
もう少し補足で説明します。あと一つ例を挙げると、時計です。昔の時計には、暗いところでも見えるように蛍光塗料が使われていたんです。蛍光塗料の成分には放射能が微量含まれていて、それが原因でものすごく嫌われていて。
そこで日本のあるメーカーが特殊な塗料を作って、それが国際標準になったんです。それはそれでよかったのですが、今度は時計のデジタル化が起こった。このような場合に工業会だけで進めていると、そこでもうジ・エンドなんですよ。
ところで、今その蛍光塗料は何に用いられているかわかりますか?実は時計に使われなくなった現在でも、別の使い道で活用されているんです。答えは、緊急避難用の掲示板です。東北大震災で津波や地震が来た際に、結局緊急避難経路が分からなかった。
「あと300mです」といったような掲示板は、昼間はいいんだけれども夜は見えないのが問題になっていたんです。安い蛍光灯だったら半年とか1年しか持たないんですよね。
であればそういった時計にしか使ってなかった技術を、我々みたいな第三者が「じゃあこういった看板に使えますよね」という風に結果的にどんどんどんどん活躍の場が増える、というようなサービスもできるんじゃないかと思っています。
ー標準化に興味があってもどうすればいいかわからないという方にとって、JIPSの第三者的な視点、そしてお客さんも巻き込んで場を作るサービスというのは非常に心強い存在なのではないかと思います。標準化は決して遠い世界で決められている他人事ではなく、自分たちも直接かかわっていくことのできる身近な自分事だということが今回よく分かりました。本日はどうもありがとうございました。

(左:藤代尚武 右:齋藤拓也)
齋藤拓也:日本知財標準事務所 所長 弁理士
日本知財標準事務所 所長 弁理士
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
藤代尚武:日本知財標準事務所 知財標準化事業部長
1982年通商産業省(現経済産業省)入省。工業標準調査室長や国際標準課長などを務め、あらゆる産業分野の標準化、認証を担当。2019年正林国際特許商標事務所に入所。現在は、国際標準(ISO)、国家標準(JIS)、団体標準などのあらゆるタイプの規格化のサポートや、認証制度の活用業務等に携わる。


