衣食住から娯楽にいたるまで、幅広い領域に関わっている「標準化」。その範囲は国際的なルールから一企業レベルの社内規則までさまざまです。近年では標準化への意識が高まり、自社の製品やサービスの規格制定に注力する企業が年々増えてきました。
しかしながら、企業や団体が標準化を目指すビジョンは一つではありません。そこで、この記事では標準化の概要を説き、メリットとデメリットについても解説します。
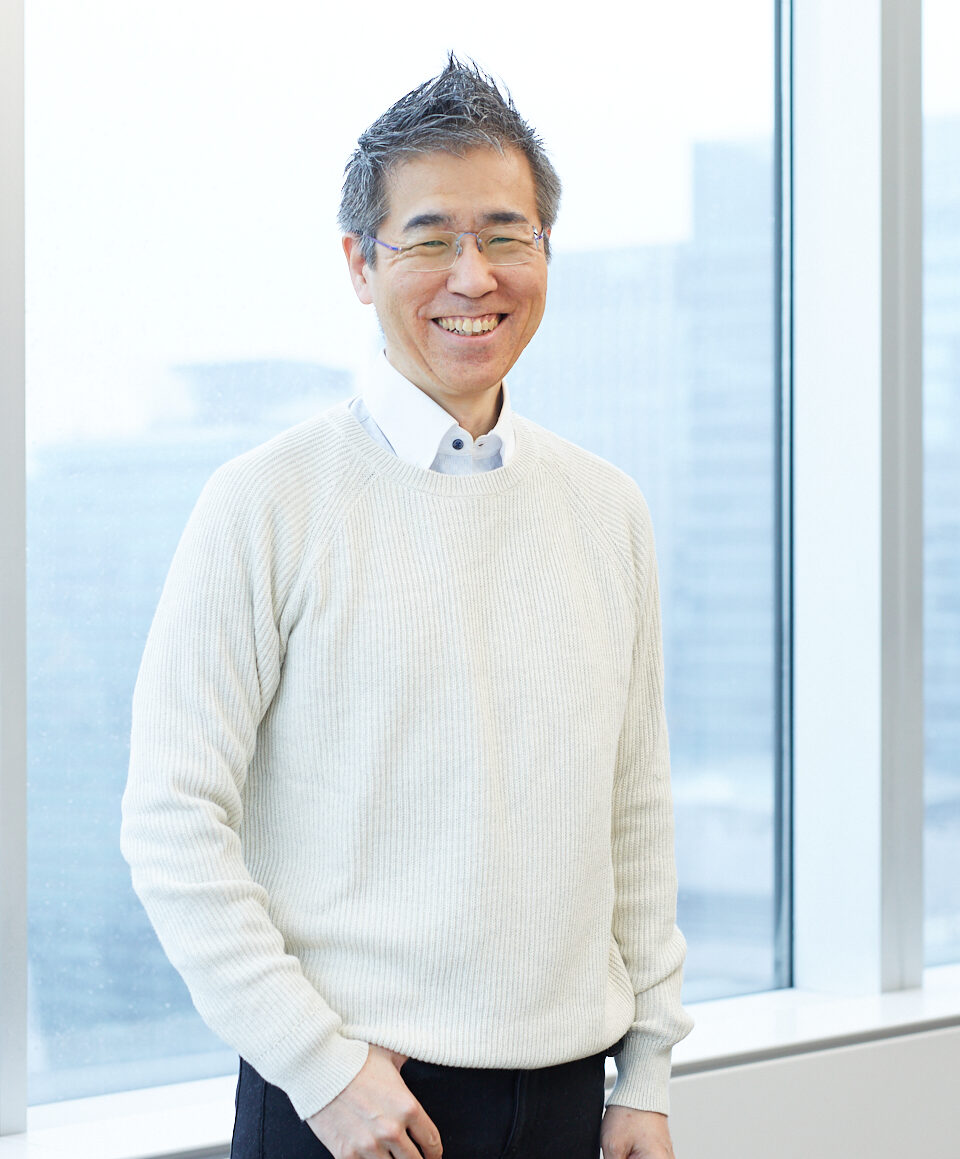 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。標準化の概要
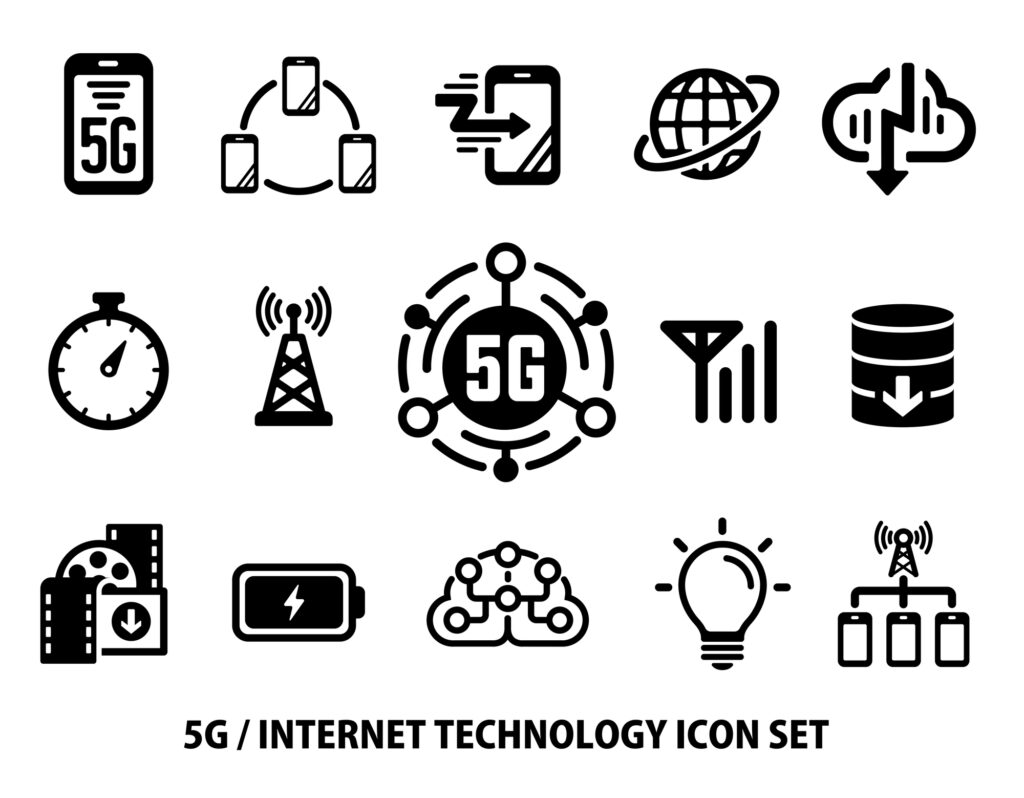
まずは標準化について大まかな歴史を振り返り、どのような案件が対象であるかを確認していきましょう。
1-1.標準化の歴史
標準化は、製品、機械や業務の仕組み、サービスのオペレーションなど、幅広い案件が対象となっています。
標準化にまつわる法律が制定されたのは1949年。当時は「工業標準化法」の名のもとに、鉱工業の製品や品質、材料、寸法、形状などが対象となっていました。また、日本国内の標準規格を定める「JIS規格」も「日本工業規格」という名称で運用されていました。
国内の標準化に転機が訪れたのは2019年。技術の進歩や社会情勢の変動などによって標準化となる案件の対象が拡大されたのです。これに伴い標準化の法律である「工業標準化法」は「産業標準化法」に、JISの「日本工業規格」は「日本産業規格」へと生まれ変わったのです。
対象案件の拡大
1-1.で解説した通り、改正前の標準化法で対象となるのは主に鉱工業にまつわる製品や事柄などが中心でした。しかしながら2019年の法律改正後にはその対象が拡大。
鉱工業だけでなく、ソフトウェアやプログラムといった無形の製品や仕組み、品質管理などのマネジメントシステム、サービス業のオペレーションなど、幅広い領域で標準化が推進されることとなったのです。
標準化のメリット
それでは標準化を推進するとどのようなメリットが得られるのか、消費者と企業・団体の双方の視点で確認していきましょう。
消費者側のメリット
標準化は、個人・社会の生活が快適かつ効率よく送れることを目的に推進されています。私たちの身近なところでさまざまなものが標準化されており、何気ない生活の一場面でメリットを得ています。
互換性の確保
たとえば乾電池。単一・単二など電池の単位が同一であれば、異なるメーカーの製品であっても形状は同じであり問題なく使用できるようになっています。
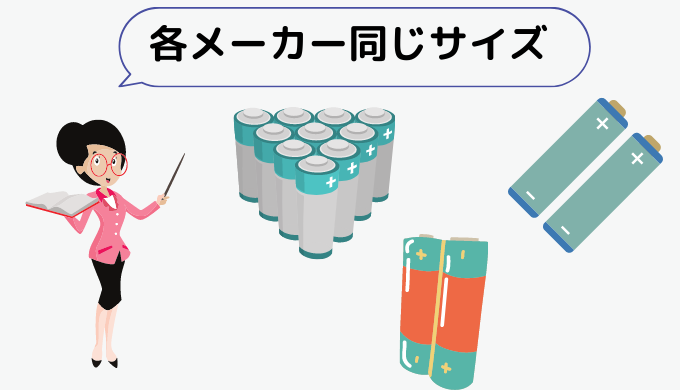
同じ単一電池という名前でも、もしもメーカーごとに形や大きさが異なればそうはいきません。標準化の規格により定められているからこそ、私たちはメーカーを限定することなく価格などさまざまな要素を比較した上で電池を自由に購入することができるのです。
品質の確保
たとえば電子レンジ。製品によってプラスアルファの機能が搭載されている商品も多く目立ちますが、高周波加熱専用であること、また電圧や周波数など、基本的な性能の基準はJISにより定められています。
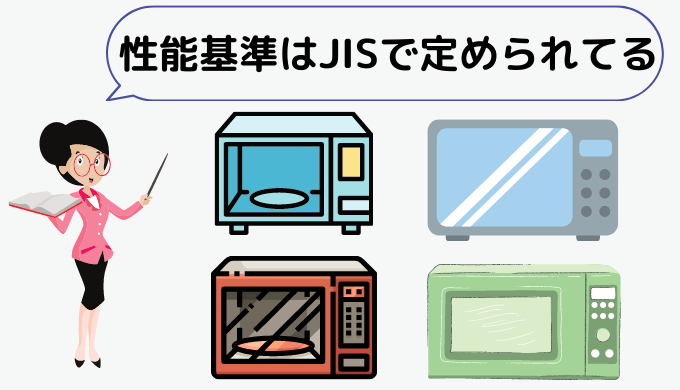
これによって電子レンジであればどの製品でを購入しても一定の品質、性能であることが保証されているのです。
安全性の確保
たとえばチャイルドシート。使用法律で義務付けられている製品だからこそ、その性能に安全性が保証されていなければ意味がありません。
身長や体重などをベースに安全基準が設けられていますが、近年では未認証のチャイルドシートがインターネット上で売買されていることから国土交通省が注意を呼びかけています。
情報の共有
たとえば道路標識。逆三角形の赤いデザイン、「止まれ(STOP)」の標識などは車を運転しない人でも日本語または英語を読める人であれば平等に認識しているでしょう。
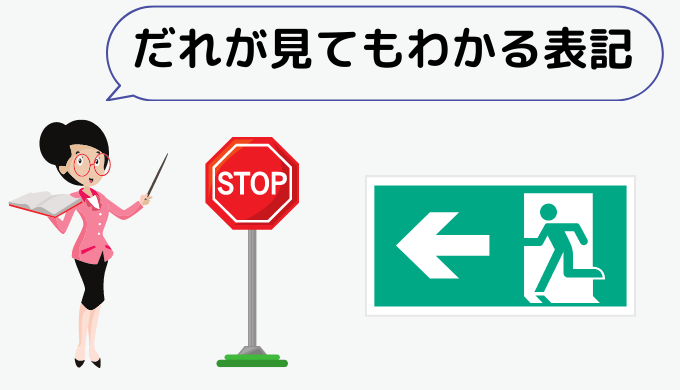
さらに緑色が特徴の「非常口」の看板デザインは日本発であり、国際標準規格として制定され世界中で使用されています。
高齢者・障害者への配慮
たとえば点字ブロックや車椅子用のスロープ。こうしたバリアフリーの設備も標準化されているからこそ幅広い人々の使用が望めます。

もしも点字ブロックのサイズが駅ごとに大きく異なっていたり、スロープの角度に極端な差があったりすれば、せっかくの設備も安心して使用できなくなってしまいます。
しかしながら点字ブロックの点字パターンは現状JIS規格のものとそうでないものが混在しており、内容に誤りのあるケースもあることから問題視されているという側面もあります。
環境の保護

転用元:経済産業省
たとえば省エネルギーラベル。省エネ法で定められた基準に対し、対象の製品がどれだけ目標を達成できているかをパーセンテージで示すラベルです。
利便性の向上

たとえばQRコード。スマートフォンのカメラなどで簡単に読み取りさまざまな情報にアクセスできるこのコードは株式会社デンソーウェーブが開発し、国際標準規格としてISOに制定されています。
企業・団体側のメリット
次に、何らかの案件を標準化させた企業や団体側の目線で得られるメリットについて解説します。
2-2-1.新市場の創造および市場の拡大
標準化の数あるメリットの一つに、新たな市場を創造できるという点があります。標準化のメリットで解説したような事例はいずれも私たちの生活に根付いたポピュラーな案件ですが、標準規格が制定された案件の中にはいわゆる先端技術も数多く存在します。
たとえば、優れた技術を持っているのにあまりにも革新的なシステムであることから比較・判断材料がなく、試験方法なども確立されていないことから営業活動がうまくいかないという課題を持つ中小企業。
この課題を解決するために、自社の技術レベルを証明するための規格や試験方法を標準化させる企業が近年増えています。
これにより、企業は業界内外での信頼性を獲得すると共にこれまでになかった新たな市場を創造できたり、海外を含む既存の市場の拡大に成功したり、大きなメリットを得られるようになるのです。
▶︎企業の標準化活用事例集!市場創造・拡大成功についてはこちら
認証事業による収益の獲得
2-2-1.のように前例のない革新的な規格による標準化を実現させると、業界の「ルールメーカー」として認証事業による収益を獲得することもできます。
そのためにまず必要なのは、人員を募って認証団体を作り、認証制度を立ち上げること。そして規格に準ずる製品に認証マークなどを付与し、消費者に対して品質保証をアピールすることでブランディングを行なうこと。
認証制度を設けることで技術者向けの研修やそれに伴うテキストの作成なども必要となります。こうした工程を確立させることで協業メーカーからライセンス料などを得て、広く収益を獲得するという方法もあるのです。
標準化のデメリット
最後に標準化を推進する上で起こり得るデメリットについて解説します。
シェアの縮小および価格競争の激化
標準化を推進することは、その規格に含まれる技術をオープンにするということです。すると追随した後発企業が多く参入してシェアが縮小したり、品質が均一化することにより価格が下落したり、といったデメリットが発生しやすくなります。
時間とお金の消費
標準化を実現させるにはお金と時間がかかります。費用と期間の短縮に繋がる「新市場創造型標準化制度」などの支援制度もありますが、それでも知見がない状況で標準化を推進するには付け焼き刃の知識では成功しないでしょう。
まずは自治体の窓口や弁理士などへ相談を行ない、アドバイスを受けながら堅実に取り組んでいくことが大切です。
まとめ
日用品から革新的な先端技術まで、幅広いものや事柄に適用される標準化。費用や時間がかかるというデメリットもありますが、それ以上に生活の利便性向上や企業の維持・発展を図る意味で、標準化はさまざまなメリットが得られます。
標準化を検討するならば、規格制定をゴールに据えるのではなく、制定した先にどのようなメリットが得られるのか専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
参考元:身の回りにあるJISの事例|内閣府/標準化の概要|経済産業省

