近年、国内企業間でオープンイノベーションの波が広がっています。しかしながら「オープン」「イノベーション」というわかりやすい二つの単語が組み合わさっていることで、さまざまな解釈ができてしまうことも事実です。この記事ではオープンイノベーションの概要とメリットを解説し、企業の具体的な事例も紹介していきます。
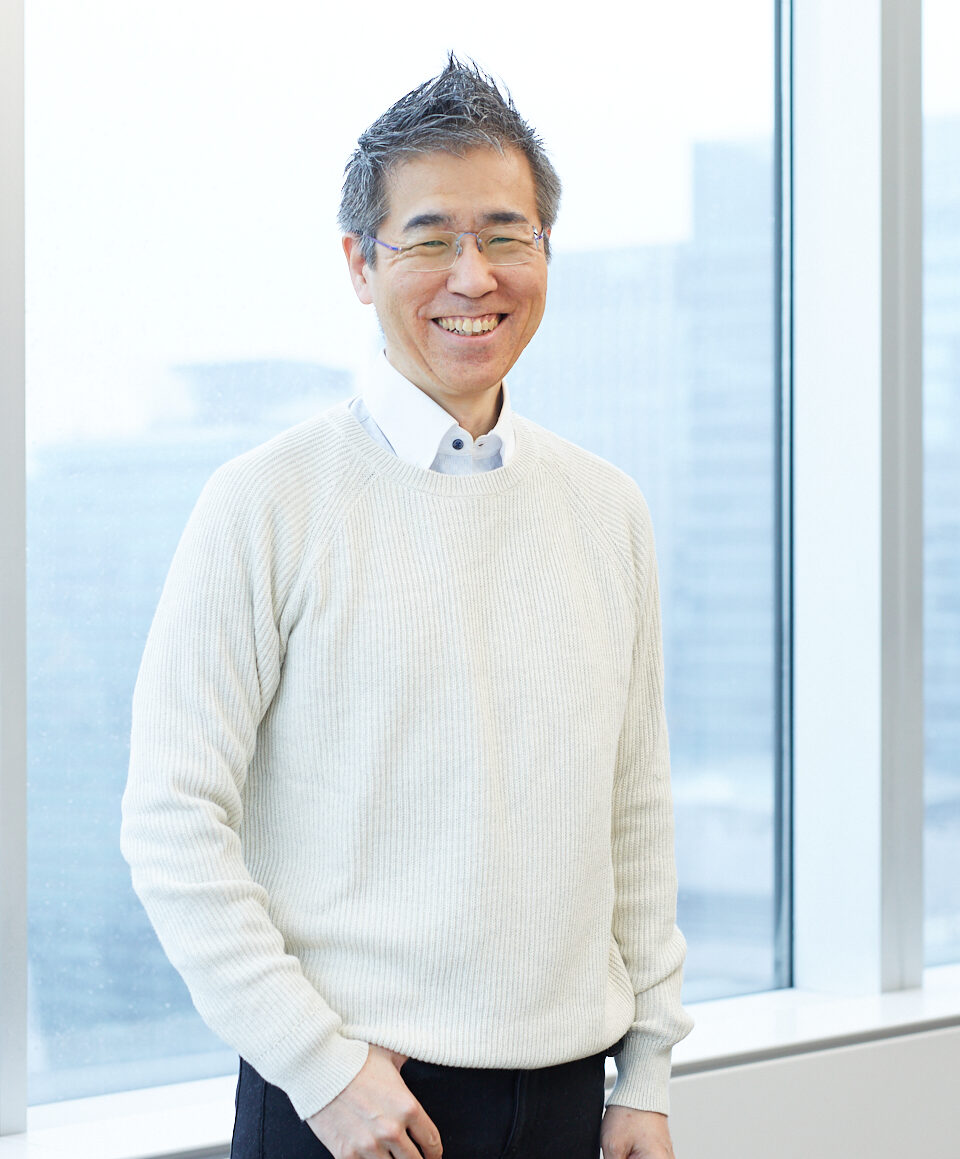 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。知っておきたいオープンイノベーションの基礎知識

オープンイノベーションとは、「企業の内外で事業アイデアや技術を融合させ、革新的な価値を創造すること」です。この定義に産学連携プロジェクトやメーカーの共同開発製品などを思い浮かべた方も多いでしょう。
もちろん、これらの取り組みもオープンイノベーションの一つです。つまりオープンイノベーションの概念そのものは従来から存在していたといえます。では近年なぜオープンイノベーションが大きく注目されているのでしょうか。それは時代の変化に伴う技術開発の課題にありました。
従来の技術開発における課題とは?
スマートフォンの普及やSNSなどの発展により、情報伝達のスピードが格段に速くなった昨今。これまで見えづらかった消費者の声が可視化され、多様なニーズが存在することがわかってきました。
これまでの国内企業の主な開発スタイルは、時間をかけてでも優れた製品を研究開発し、その権利を自社で保護・独占するというものでした。しかしながらテクノロジーの発達により高度な技術が広く一般化した現在、従来の方法では利益を得ることが難しくなってきました。
たとえば技術者が閉鎖的な環境で何年、何十年と研究開発を続けているとします。その努力が実を結び、念願の製品化にこぎつけることになりました。その一方で実はすでに類似の発明が他社で編み出され、権利化され、市場に普及しつつある──こうしたケースは決して珍しくないでしょう。
企業を永続的に発展、維持していくためには会社の規模を問わず時代の変化を敏感に察知しなければなりません。開発スピードを向上させて多様化するニーズにいち早く応え、消費者の「こんなものがあったらいいのにな」という声を形にしていくことが重要なのです。
しかしながら企業の人員や資金には限りがあります。仮にその双方を満たしていたとしても、満足な成果を得られるだけの体制を作るまでには多大な時間がかかるでしょう。そして同じコミュニティに属する社員だけではアイデアはやがて先細り、高い目標を達成するための突破口も見つけられず行き詰まってしまうこともあるでしょう。
こうした状況で現場の社員ならこのように感じるかもしれません。
オープンイノベーションが注目されている理由の一端──それは「特別」な枠組みであった企業や団体、個人間での連携を「日常的」なものとして取り入れていくことによって得られるメリットの大きさにあると言えるのです。
オープンイノベーション導入のメリット

それではオープンイノベーションを取り入れることによって得られるメリットを具体的にあげていきましょう。
2-1.新たなアイデア、技術、知識の獲得
外部との意見交換や協業は、自社内の業務やコミュニケーションだけでは得られない斬新な視点による意見や、専門外の技術・知識に触れられるチャンスです。
もちろん、これらは社員が任意でセミナーなどに参加したり、特別なプロジェクトで交流を図ったりすることでも得られるメリットではあります。しかしながらこうした取り組みを恒常的に行なうことで、常にアンテナを高く掲げ、広い視野を獲得することに繋がっていくのです。
事業推進および開発におけるスピードアップ
2-1.で解説した知的財産の獲得が可能になると、一人ひとりの観点がブラッシュアップされていきます。従来の方法では見えてこなかったアイデアや開発方法にも迅速に辿り着ける可能性が高まり、事業を推進していくスピードもあがっていくことでしょう。
また、外部の協力や技術の向上によって開発スピードそのものも迅速になります。さらには専門外の知識をゼロの状態から学ぶ時間や資金を削減することができ、コストカットにつながるといえます。
競合他社とのさらなる差別化
新たなアイデア、技術、知識を獲得し、短期間・低コストで開発を進められることで競合他社との大きな差別化を図ることができます。自社の資源だけで取り組んできたこれまでよりも欠点を補い、鮮度の高い製品やサービスを迅速に提供できる──こうした相乗効果によって一歩先ゆく事業展開を広くアピールすることができるのです。
オープンイノベーションの導入事例

それでは国内の企業がどのような方法でオープンイノベーションに取り組んでいるのか、具体的な事例をもとに解説していきます。
地元企業とのコラボレーションを通じた知財戦略
1951年に設立された中国電力株式会社。電力会社として中国地方の5県を中心とした事業展開を行なう同社では、地元企業と協業することによる『知財マッチング』を推進しています。
『知財マッチング』の目的は、地元企業に自社の知的財産を積極的に活用してもらうこと。しかしながら権利化業務や知財の売り込みなどが重視されてマッチング業務に時間を割けない状況にあったといいます。そこで2017年、同社のエネルギア総合研究所内に新設されたのが「事業支援グループ」です。
このグループでは共同研究先を見つけるための特許分析調査、共同開発先の特許分析、知財マッチング先とのコーディネイトなど、オープンイノベーションを進めていくために必要なコンサルティング業務が行なわれています。
この取り組みが軌道に乗り、自社の知財を一方的に展開するだけでなく多くの知的資源を獲得できたという同社。他社の技術、知財、ノウハウなどを収集しながら協業相手の発掘を積極的に行なえるようになったそうです。
電力会社の技術開発は以前からメーカー共同開発が主流であり、従来からオープンイノベーションの形態が確立されていたといっても過言ではありません。
こうした取り組みによって競合他社との優位性がより確立されていったという同社。電力小売の自由化などの情勢変化にも臨機応変に対応しながら躍進を続けています。
まとめ
他社との協業を積極的に行なうことで、革新的な価値を創造していくことのできるオープンイノベーション。これまで特別視してきた共同開発などが身近な取り組みとなることで、企業も社員一人ひとりも大きなメリットを得られることがわかりました。
もちろん情報の漏洩や利益の分配問題といった新たな課題も生じますが、これらのリスクを戦略的に回避しながら導入を進めることで企業はより大きく飛躍していけるのではないでしょうか。

