一般的に財産と聞いて想像するもの──たとえばお金や宝石、土地、美術品などを思い浮かべる方が多いでしょう。そうした形あるものではなく、アイデアや発明、創作物など、人が考えついた経済的価値のあるものを『知的財産』といいます。
また、『知的財産』を活用して事業展開などに役立てるための計画のことを『知財戦略』といいます。この記事では『知的財産』の基礎知識と、企業の『知財戦略』について事例を踏まえながら解説します。
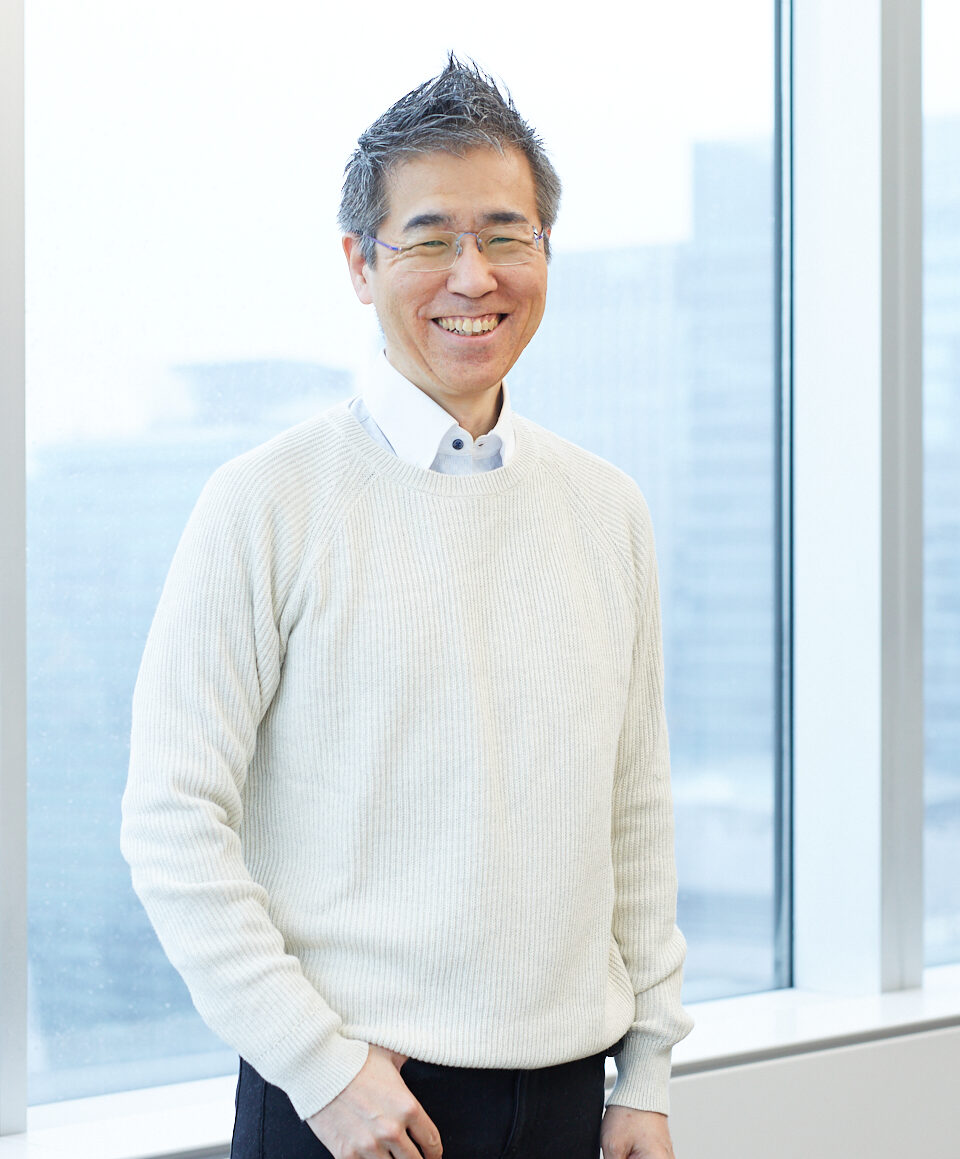 当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。
当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士
齋藤 拓也
1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。企業に関わりの深い『知的財産』とは?

『知的財産』の中でも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を『産業財産権』といいます。『産業財産権』の管轄は特許庁。企業や団体、個人などが考えついた技術やデザイン、ネーミングなどについて独占的な権利を与えることで模倣を防止しています。さらに、それらの価値を高めることで信用の向上や産業の発展に寄与することを目的としています。
▶︎知財で利益を最大化できる!活用方法と事例についてはこちら
『産業財産権』の主な内訳
『産業財産権』は権利ごとに特許法によって要件や権利を保有できる期間が定められています。
特許権
自然法則を利用した高度かつ産業上で利用可能な発明。たとえば携帯電話の通信システムなどが該当し、近年では新たな通信システムである5Gにも規格特許が存在します。特許権が認められると、出願日から20年間は発明を独占できます。一方で、発明内容は公開特許公報などで誰もが閲覧できるようになります。
実用新案権
物品の形状、構造、組み合わせなどに関する発明。たとえば折り畳んで捨てやすいミシン目入りのティッシュ箱などの例があります。製品の製造方法など技術そのものは対象外です。権利の保護期間は出願日から10年間。無審査で登録できるため、権利を侵害された際には実用新案技術評価書の準備などで訴訟までに時間を要します。
意匠権
物品の形状、模様、色彩、またはそれらの組み合わせからなるデザイン。洋服や電化製品のデザインなど幅広く該当します。さらに「画像」や「建築物」、「内装」も新たに保護対象となりました。権利の保護期間は出願日から最長25年。これまでは登録日から20年でしたが、法律改正に伴い2020年4月1日以降の出願から25年に延長されました。
商標権
企業や製品、サービスなどを見分けるための目印。企業やブランドのロゴなどが該当します。先に他人が類似のものを出願・登録していないことや、産地や品質などを表示するものは登録されない等の決まりがあります。
例外として、特定の組合等は、地域の名称に商品等の普通名称を組み合わせた場合等は商標登録することができます。権利の存続期間は設定登録日から10年間ですが、10年ごとに何度でも更新が可能です。
中小企業ならではの知財戦略

日本では特許権を筆頭に、『知的財産』を保有しているのは大企業が中心というイメージが根強い状況です。しかしながらリーマンショックや自然災害などによる不況を経験し、近年では自社の存続を懸けた『知財戦略』を展開する中小企業が増えています。ここでは企業の具体的な2つの事例を確認していきましょう。
事例1.逆境を乗り越え再認識した『知財戦略』の重要性
アルミ合金製はしご・脚立の製造・販売を手がける株式会社ピカコーポレイション(大阪府東大阪市)。業務用はしごや脚立・作業台で国内トップシェアを占める企業です。
同社の目標は「1製品1権利(特許権)プラス意匠権」。アルミの形状から厚みや強度まで自社で設計しており、開発前の先行技術調査には特に注力しているのだそうです。調査に利用しているのは、主に公開特許公報とJ-PlatPat。さらに知財意識の向上促進のために特許庁のセミナーにも参加しているといいます。
そんな同社では以前、同業他社から意匠権の侵害で訴訟を起こされた苦い経験があります。当時から開発前の先行調査を徹底していたものの、その意匠が類似にあたるという認識はなかったそう。さらに調査を進めて類似にあたらない旨を主張しましたが、裁判所は「完全に非類似であるとは認められない」という判断を下し、最終的には和解となりました。
この経験を通じ、同社は意匠権をより念入りに確認するようになったそう。それまで「意匠権よりも特許権のほうが権威がある」という認識でいたそうですが、「思想を表した特許権よりも見た目が基準となる意匠権のほうが判断しやすい」と考えを改めたそうです。実際に、類似品の輸出入なども意匠権に該当する形状や構造のほうが税関で判断しやすいという特徴があります。
さらに同社ではこの訴訟を経て営業と開発の連携が深まったのだそう。係争中の開発担当者を目の当たりにした営業担当者が権利関係の事前調査がいかに重要であるかを理解し、開発部隊に対する情報提供などをこれまで以上に積極的に行なうようになったそうです。
逆境から絆が育ち、より慎重かつ強固な『知財戦略』が展開できるようになった同社。今後もますますの躍進が期待できそうです。
事例2.知財人材の育成で未来へ投資する『知財戦略』
オフィス・文化施設関連設備の製造・販売を手がける金剛株式会社(熊本県熊本市)。50年以上前から知財戦略に取り組み、他社との差別化を図ってきました。
同社は事例1で紹介した株式会社ピカコーポレイション(大阪府東大阪市)と同様に、特許権と意匠権の両方に力を入れています。意匠権は主に海外の模倣品抑止、特許権は権利範囲を広くとることで国内での使い勝手をよくしていこうという想いからです。
こうした取り組みは外部からも評価されやすく、図書館、博物館、官公庁といった入札案件において受注の切り札となっています。また、新たなマーケットの拡大にも地道な権利取得の成果が顕れているようです。
そんな同社は2015年に開発グループを新設。データや進捗などの工程を明確に把握できるようになったことで自社製品の強みや特徴が認識しやすくなり、知財の出願の際にアピールするポイントが掴みやすくなったといいます。
また、知財への意識を担当者間だけで完結させることなく、勉強会を開くなど積極的な社内教育を行なっているそう。開発グループが一丸となり、権利が消滅したものも含めて同社が過去に出願した案件をリストアップし、自社の知財を見つめ直しながら意見を出し合っているそうです。
国内の中小企業の多くは知財に関する専門知識を持つ社員がおらず、弁理士任せになっていたり、『知財戦略』への意識が薄かったりと、課題が多い状況です。そうした中でも50年以上前から『知財戦略』を展開し、知財が自社の実績の飛躍に貢献していることを体感してきたという同社。今後も知財人材の育成と全社員の知財意識の向上を図り、ますます前進していくことでしょう。
まとめ
中小企業にとって、敷居の高さを感じてしまいがちな『知的財産』。しかしながら、ネームバリューや資金が限られているからこそ自社の技術を保護し、有効活用することが企業を永続させらるための武器となるのです。
『知財戦略』が必要であることを頭では理解していても、何から始めたら良いかわからない──そんな時にはまず弁理士事務所や官公庁の支援窓口への相談、特許庁のセミナー参加などを行なってみてはいかがでしょうか。自社に必要な『知財戦略』の足がかりを見つけて将来的な飛躍へと一歩前進するカギがきっと掴めることでしょう。
参考元:Rights|特許庁

